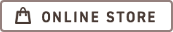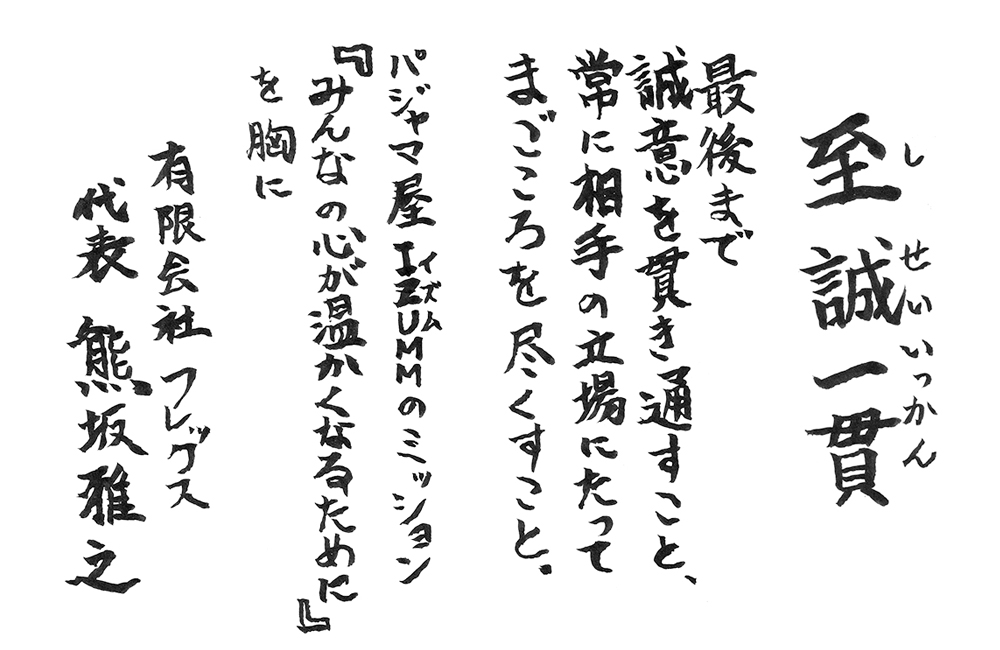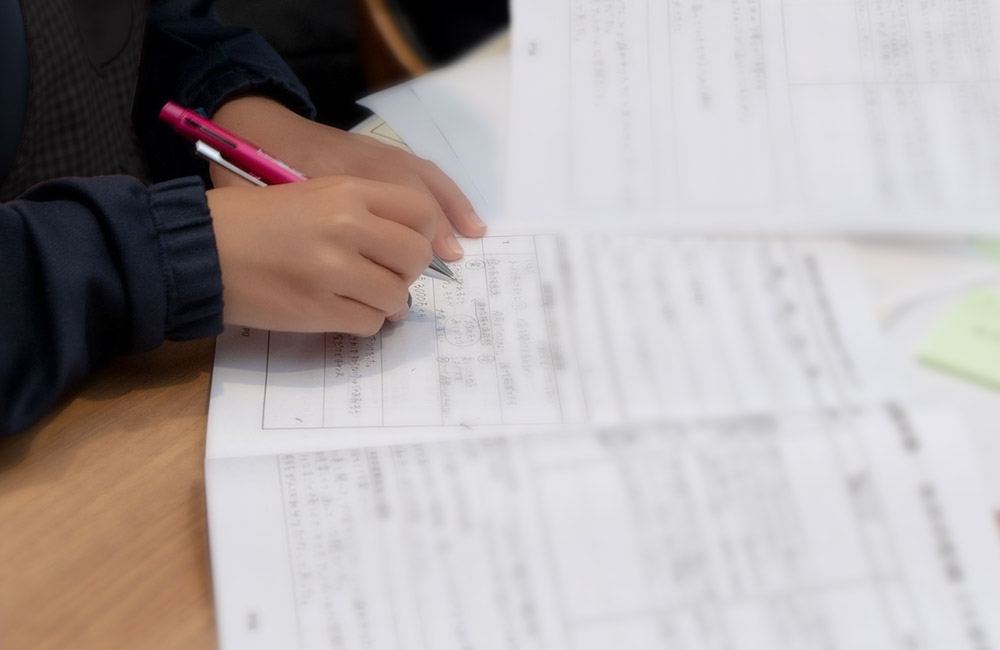季節は二十四節気の雨水(うすい2月19日)へと移り、雪は雨に代わり、土は潤い始め、草木が芽吹き始める時期とされていますが、今年は雪が多いようで、降雪地帯の方は大変な思いをされているのでしょう。日本海側の地域では「春の七雪」という言葉があり、立春を過ぎても、七回は雪を見てやっと春になる、という意味だそうです。なるほど、雪国の人の雪との付き合い方が良くわかるような言葉です。3月に入り、春の気配の中に降る雪は「なごり雪」、他にも、雪のつく言葉は美しい響きのあるものが多くあります。細雪、淡雪、ぼたん雪、根雪、など、その情景が良く見えるような、自然に寄り添う思いが言葉を紡ぐのでしょう。



ずっと追いかけている、二十四節気と七十二候、これらは元々東洋哲学の「人間は自然の気を受けて生きているので、季節の働きに合わせた生活を守ることが大切である」という思想が元となっています。その思想から季節による養生法が紹介され、それらが中国より伝わりました。3世紀ごろまでは、気象や動植物の変化から作られた自然暦を使っていた日本ですが、それ以降、様々な暦を併用し、「宣命暦(せんみょうれき)」という暦が江戸時代前期まで使われ、その後、月の暦と太陽の暦を合わせた、太陽太陰暦の「天保暦(てんぽうれき)」が明治初期まで使われ、暦が太陽暦となっても「旧暦」として一般に用いられました。古代中国で作られた二十四節気は、冬至から冬至を24分割するというもので、それらの暦の日付と季節感のずれを調整するために併用されました。さらに七十二候は、二十四節気をさらに、初候、次候、末候と三等分してほぼ5日ごとの動植物を含む自然の変化を日常生活の目安にしたものです。こちらも、やはり紀元前中国で発生したものですが、日本人の生活に合わせて、江戸時代後期に作成されました。

たとえば、二十四節気は雨水の今、七十二候は初候が土脉潤起(雨が降り、土が潤いだす)、次候は霞始靆(霞がたなびき始める)、末候は草木萌動(草木が芽生え始める)、となります。常用漢字ではない字が現れたり、読み方が難しい場合もありますが、漢字を見ているだけでも、なんとなくその季節の動きがわかるような気がして、この春の候わくわくしませんか?紀元前中国の人が感じていたこと、江戸時代の市井の人々の感じていたこと、そして、私が春の訪れに感じる胸躍る気持ちは、皆同じということにびっくりします。


と、今日もそんな、いにしえの景色に妄想を膨らませながら初春の夜を過ごしています。こんなことを考えていると、今夜は面白そうな夢が見られるかしら? 皆様もこの春の宵、ぐっすりとお休みください。
参考文献:村上百代著 二十四節気に合わせ心と体を美しく整える ダイヤモンド社
染谷雅子
ガラス作家・アロマセラピスト 染谷雅子
ギャラリーはなぶさ https://www.hanabusanipponya.com
作品名:「お雛様」