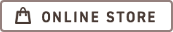冬がやってきます。二十四節気は立冬(りっとう11月8日)を迎えます。七十二候は、山茶始開(つばきはじめてひらく11月8日~12日) 地始凍(ちはじめてこおる11月13日~17日) 金盞香(きんせんかさく11月18日~21日)と、続きます。冬の入り口にツバキ(サザンカの意)が咲き始めるも、その足元は、温度が下がり地中の水分が凍ることで、地面は白く幻想的な景色となり、地中の栄養を貯めたキンセンカ(スイセンの意)はあちらこちらで群生する、そんな晩秋から初冬の森の様子を表した候となります。 

IZUMMフリース 2wayネックウォーマー レディースパジャマ
秋と冬のはざま、先日も晩秋の雷の音で目を覚ましました。お転婆な春雷と違い、そろりと冬を連れてくるような朝の雷鳴。季節は動き、11月、霜月(しもつき)となりました。霜の降る月の意で、旧暦の11月として名づけられたものです。11月はほかにも異称が多く、冬の始まりらしく雪待月(ゆきまちづき)や神楽月(かぐらづき)、そして、神帰月(かみかえりづき)とも言われます。神帰り月ということは、神がいなかった時期がある訳で、そう、10月は神無月(かんなづき)です。この月はすべての神様が出雲へ集まるので神がいない月の意味となり、出雲地方では神在月(かみありづき)と呼ばれます。素敵な日本の言葉。