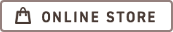あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
皆様、年末年始といかがお過ごしでしたでしょうか?地域によっては大雪になったようですが、ここ関東南部ではきれいな青空の元旦とちょうど良いお湿りで、おしなべて穏やかな年明けとなりました。二十四節気は年明け最初の節気として、すでに、小寒(しょうかん1月5日)を迎えています。七十二候は、芹乃栄(せりすなわちさかう1月7日~9日頃)、水泉動(しみずあたたかをふくむ1月10日~14日頃)、雉始雊(きじはじめてなく1月15日~19日頃)となります。小寒は「寒の入り」ともいわれ、寒さが本格的になることを意味し、節分までが「寒」となります。冬至を過ぎ、昼の時間がほんの少しずつ長くなっていることも気づく余地もなく寒さは厳しくなる頃ですが、水辺では、セリが生えはじめ、その根元で凍っていた湧き水は大地の温もりで溶け、動き出します。そして、耳にはキジがつがいの相手を求める鳴き声が届くころ。極寒の時でも、表層に現れる寒さのしるしの裏側では、必ず温もりが出番を待っているという、自然の摂理、季節の巡りを知ることができる候となります。

いよいよ仕事始め。心機一転、すっきり、はっきり、気持ちも引き締まり、元気に行きたいところですが、なんとなく、だるさを感じている人もいるのではないでしょうか。もしかしたら、「正月ボケ」と言われる状態かもしれません。原因は食生活や生活習慣の乱れが考えられます。特に、今年は「奇跡の9連休とも言われた長い休みになりましたので、影響は大きいかもしれません。
抜け出すためには、
①朝起きたら、まずカーテンを開けて朝日を浴びること。太陽光を浴びると、脳内物質セロトニンが生産され、体内時計の調整に役立ちます。窓を開けず、外出の準備をすると、この作用も得られませんので注意です。
②出かける前に朝食をとること。内臓の動きが活発になり、体が目覚め、1日過ごすための体温を高め維持します。
③軽い体操をする。深呼吸をして、首を回したり、肩の上げ下げ、背伸びをしたり、軽い柔軟体操などで体は目覚めます。
まずはこの3点で心身をしっかり目覚めさせて、今日1日に挑めば、「正月ボケ」も解消できるはずです。 
かく言う私も、お正月には毎日のお客様で良く食べ、良く飲み、よく笑い、楽しく過ごし、すっかり昼夜逆転のような生活になり、只今、生活回復訓練中です。 毎年のことですが、クリスマス、大掃除、正月の準備、そして大晦日から元旦、三が日、と年末年始の毎日のなんと目まぐるしく、悩ましく、そして、心躍るのでしょう。

母は季節の行事を大切にして、子供の頃、できる限りのことをしてくれました。クリスチャンだった彼女はこの時期をとても丁寧に過ごしていました。でも、お正月の神様も大事なので準備も多くなります。父もそんな母がすることを楽しんでいたのでしょう、いつも見守ってくれました。決して裕福だったわけでもなく、すべてのことを母一人で采配するので、忙しかったことでしょう。12月に入ると、いろいろな果物やドライフルーツをブランデーや自作の梅酒に漬け込み、クリスマスのケーキの準備が始まります。あの頃は、お歳暮に新巻鮭が送られることが多く、それをさばいて、麹に漬け込んだり、なますにしたりと、正月膳への準備です。そんな姿を見て、私は大人になったらこんなにたくさんのことを、本も見ずにできるのかしら…、と思ったものです。私たちが活躍できるのは、天井の埃払いから始まりガラス拭きへと続く大掃除ぐらいで、これも作ってもらった揃いの三角巾とエプロンをつけて家じゅうを行進していました。29日の夜からは、黒豆炊きから始まる正月料理の準備です。年賀状は必ず母自作の木版画で、ただ、投函するのはいつも大晦日かその前の日…、その点は今の私と同じです。 少し成長してからは、クリスマスの準備やお正月の料理の準備なども、教えてもらいながら手伝いができるようになり、母が逝った今、私なりに身についた習慣となりました。 
クリスマスはとても大切にしていて、食後のケーキの前に「きよしこの夜」を歌い、一番若い人がお祈りをするので、妹がその役を担っていました。今でも、毎年、家族でクリスマスを迎えます。人が増えたり減ったりまた増えたり…、家族の歴史は続きます。お祈り役も妹から、姪になり、甥になり…、去年のクリスマスも賑やかに大集合でした。 まだまだ、母の采配には追い付きませんが、クリスマスの定番キッシュの焼き上がりを待つ時、お正月のゆり根きんとんを練っている時、煮物の里芋の皮をむいている時、お屠蘇の準備をする時、窓ガラスを吹いている時…、様々な情景で母を思い出します。 想いを家族や友達皆で分かち合い、健康と小さな幸せを確認しつつ祈る。それが、正しいお正月の過ごし方…、と、当たり前のことを、改めて思う今年のお正月でした。 
さて、七草粥の準備をしなくちゃ、そうそう、うちのお粥はセリが多いのよね…、また思い出しつつ、そろそろ眠りにつこうと思います。
皆様、今夜もぐっすりお休みください。
染谷雅子
ガラス作家・アロマセラピスト 染谷雅子
ギャラリーはなぶさ https://www.hanabusanipponya.com
作品名:「フュージンググラス 帯留め」